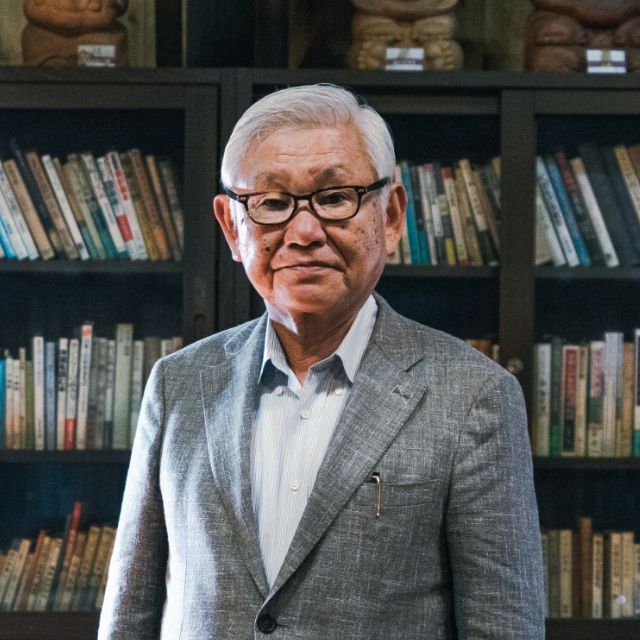お湯割りは、
薄めることではありません。

美味しいお湯割りは、何よりも温度とアルコール度数が大事です。
アルコール度数25度の焼酎を、焼酎6にお湯4で割ると、
アルコール度数は15度程度になります。
これは清酒と同じくらいのアルコール度数で、
日本人にはこれくらいのアルコール度数が合うわけです。
そして温度もちょうど40℃前後になります。
人が甘みを感じるのは35~40℃ですので丁度いい。
さらに温かいと、焼酎の美味しさの成分が引き出されます。
焼酎の99.7%をしめているのは、水とアルコール。
その残りわずか0.3%ほどが味や香りとなる成分で、
これがそれぞれの焼酎の個性をつくります。
これらの成分は、お湯を入れて温度を上げることで溶けてまろやかになります。
お湯割りというのは、アルコール度数を薄めるだけでなく、
美味しく飲むための工夫なのです。